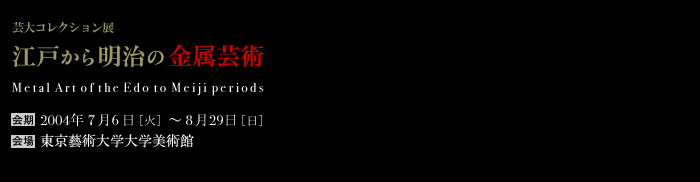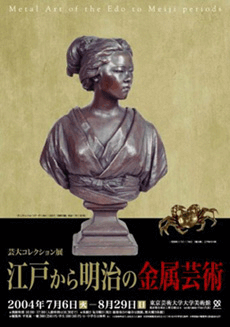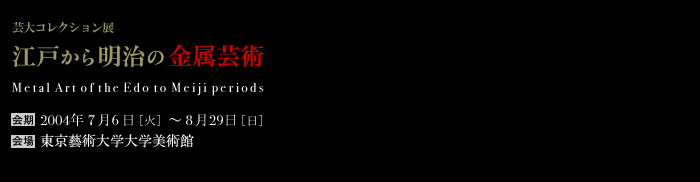 |
[開館時間] 10:00~17:00(入館時間は16:30まで)
[休館日] 毎月曜日 ただし月曜日が祝日・振替休日の場合は開館、翌火曜日休館
[観覧料] 一般300(250)円 学生100(50)円(小・中学生は無料)
*( )は団体料金で、20名以上に適用されます。
(団体観覧者20名につき1名の引率者は無料)
[主催] 東京藝術大学大学美術館
|
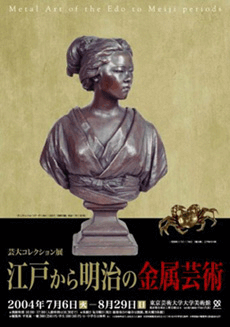 |
展覧会の概要
今秋、東京芸術大学大学美術館が開館して5周年を迎えます。
この5年間のコレクションの公開は、よく知られた名品を中心に展示してきましたが、
当館には東京美術学校開校以前から120年にわたって教育資料として収集され、
特に注目を得ないまま収蔵庫内に保管されている数多くの作品資料があり、
今後はこれらの資料を可能なかぎり有効に活用したコレクション展の充実をめざします。
その初回となる今回の【芸大コレクション展 江戸から明治の金属芸術】では、
そのようなほとんど注目を得られなかった作品を数多く出品することを目的のひとつとします。
「金属」という素材で表現された作品という主題を設定して、指より小さな刀装具や仏像から、
日本の近代彫刻史の幕開けをもたらしたラグーザ作の数々の胸像、
そして東京美術学校生の卒業制作まで、様々な形状、技法、種類の作品を約60点展示します。
明治政府が当時の万国博覧会に出品する作品のために描かせた図案集に基づくと見られる花瓶も当コレクションに含まれ、
おそらく初めて展示されるものの一つです。
日本の近代において世界的に評価された金属による「美術」作品が、
同じ上野公園で同時期に開催される東京国立博物館の「万国博覧会の美術」で展示されます。
また、国立西洋美術館で開催される「聖杯―中世金工の美術」展ではドイツの優れた金工が紹介されます。
これらの展覧会と合わせて鑑賞することで、金属という素材の多種多様で豊かな表現力を知る貴重な機会になることと思います。
|
出品目録
| 会場配布資料ファイルのダウンロード | (PDF, 105KB)
下記の内容を含んでいます。PDFの閲覧には Adobe
Reader が必要です。
|
|
1
|
|
後藤程乗 ごとうていじょう
|
1603-1673
|
|
「蟹図小柄」 かにずこづか
|
|
江戸時代前期 17c. 赤銅魚子地 高肉彫 金色絵
|
|
室町時代から続く装剣金工の後藤家9代目。裏は一面金に鑢目が施されている。
|
|
一宮長常 いちのみやながつね
|
1721-1786
|
|
「蟹目貫」 かにめぬき
|
|
江戸時代中期 18c. 銅 容彫 赤銅象嵌
|
|
作者は「東の宗珉、西の長常」と表される江戸時代の京都金工の代表的存在。
|
|
「蟹目貫」 かにめぬき
|
|
江戸時代中期 金 容彫 赤銅象嵌 石目打
|
|
打ち出した金に赤銅象嵌の目、甲羅には石目と毛彫り。格調高い技と材が全面に表出される。
|
|
「野菜図縁頭」 やさいずふちがしら
|
|
江戸時代中期 赤銅魚子地 四分一高彫象嵌 高肉彫 金・銀・銅色絵
|
|
「恵比須目貫」 えびすめぬき
|
|
江戸時代中期 赤銅 容彫 金・銀色絵 銀・銅置金 赤銅象嵌
|
|
鯛を吊り上げ、烏帽子をかぶる七福神の一人。東京美術学校初代彫金科教授加納夏雄の箱書きがある。
|
|
鉄元堂茂光 てつげんどうしげみつ
|
生没年不詳
|
|
「加茂競馬図縁頭」 かもけいばずふちがしら
|
|
江戸時代後期 赤銅魚子地 高肉彫 金・銀・銅色絵 金象嵌
|
|
正林武顕 しょうばやしたけあき
|
生没年不詳
|
|
「亀図頭」 かめずかしら
|
|
江戸時代後期 四分一地 赤銅高彫象嵌 金銀色絵
|
|
浜野保随 はまのやすゆき
|
?-1836
|
|
「蓮蛙図縁頭」 はすかえるずふちがしら
|
|
江戸時代後期 赤銅魚子地 四分一高象嵌 金色絵 赤銅象嵌
|
|
徳島藩主蜂須賀家の藩工。
|
|
石黒是美 いしぐろこれよし
|
生没年不詳
|
|
「百合図縁頭」 ゆりずふちがしら
|
|
江戸時代末期 赤銅魚子地 高彫象嵌 金銀色絵・銀象嵌
|
|
得意の赤銅魚子地に高彫色絵で百合の花と葉を表し、銀象嵌の露玉を付す。
|
|
桂永寿 かつらえいじゅ
|
生没年不詳
|
|
「百合図縁頭」 ゆりずふちがしら
|
|
江戸時代中期 赤銅魚子地 高肉彫 金・銀色絵
|
|
二代横谷宗與門下で横谷式赤銅魚子地に高彫色絵をよくした。是美の作との比較が興味深い。
|
|
後藤程乗 ごとうていじょう
|
1603-1673
|
|
「獅子香合」 ししこうごう
|
|
江戸時代 四分一 鍛造 片切彫 毛彫 鍍金 獅子は赤銅 打出 金・銀色絵
|
|
菊川 きくかわ
|
|
|
「妙見尊像」 みょうけんそんぞう
|
|
江戸時代 銀 丸彫 金製光背付
|
|
北極星あるいは北斗七星を神格化した菩薩。国土を擁護し災害を滅除し、人の福寿を増すという。
|
|
作者不詳
|
|
|
「自在蟹香合」
|
|
鉄・銀 鍛金 眼に金象嵌
|
|
自在置物の伝統を美術学校の鍛金教育に取り入れようとした岡倉天心の意を受け、見本として明治31年に購入。
|
|
香川勝廣 かがわかつひろ
|
1853-1917
|
|
「柿形香炉」
|
|
銅・四分一 鍛金 赤銅象嵌
|
|
加納夏雄の後継者として東京美術学校教官・帝室技芸員を務めた勝廣の堅実な技法を示す。
明治32年に作家寄贈。
|
|
明珍 みょうちん
|
|
|
「蟹形錠」
|
|
江戸時代 鉄 鍛造
|
|
甲冑師の技術の応用で様々な形態の錠がつくられた。
|
|
美方 みかた
|
|
|
「蝦形錠」
|
|
江戸時代 鉄 鍛造 銀象嵌
|
|
|
|
2
|
|
藤原通廣 ふじわらみちひろ
|
生没年不詳
|
|
「廻鉢形兜」 めぐりばちかぶと
|
|
江戸時代 鉄 鍛造 前立は木製漆塗 青糸威
|
|
回転する鉢で鉄砲の弾をかわす構造。とんぼは勝虫として武士に好まれた飾り。
|
|
辻重次 つじしげつぐ
|
生没年不詳
|
|
「牡丹文鐙」 ぼたんあぶみ
|
|
江戸時代 鉄 鋳造 毛彫 銀象嵌
|
|
村田整珉 むらたせいみん
|
1761-1837
|
|
「水盤」
|
|
江戸時代 18-19c. 青銅 鋳造
|
|
世界各地に散在する「整珉鋳」銘の作品。
彼の蝋型の技を示す作品として津田信夫から入手した作である。
|
|
津村亀女 つむらかめじょ
|
?-1772
|
|
「鶉香炉」 うずらこうろ
|
|
江戸時代 18c. 真鍮 鋳造
|
|
亀女といえば鶉の香炉。長崎で活躍した女性の蝋型鋳物師で、
鋳肌と鏨による仕上げを併用した表現。羽の部分が蓋となっている。
|
|
本間琢斎[二代](推定) ほんまたくさい
|
1846-1904
|
|
「柳蓮鷺図花瓶」 やなぎはすさぎずかびん
|
|
青銅 鋳造
|
|
佐渡の蝋型鋳造の祖、本間琢斎の蝋型の味を存分に発揮した作。明治38年第3回金工協会展出品。
|
|
西村雲松[初代] にしむらうんしょう
|
1859-1912
|
|
「麒麟図香炉」 きりんずこうろ
|
|
真鍮 鋳造
|
|
鋳金家初代西村雲松は工部美術学校でラグーザに彫刻を学び、
その後は輸出向けの鋳造作品に従事した。独特な蝋型の透物を得意とし、
本作にもその技量が示される。
|
|
「女神図メダル」
|
|
青銅 鋳造
|
|
裏の鋳銘「明治十一年四月旧工部美術学校入学試験製作品 西村雲松造」。
|
|
作者不詳
|
|
|
「両耳花瓶」 りょうじかびん
|
|
青銅 鋳造
|
|
北宋の12世紀前半に編纂された「宣和博古図」あるいは、
これを参考にした「温知図録」に見られる銅器の図案を元に制作された作。
|
|
黒川栄勝 くろかわえいしょう
|
1854-1917
|
|
「龍飾銀盃」
|
|
明治29年(1896)銀 打出 鋳造
|
|
栄勝は明治鍛金界屈指の作家として挙げられるが、現存する作例が少ない。
本作のその貴重な例であるが、鋳造が主役であり、他の作例の確認が待たれる。
|
|
作者不詳
|
1854-1917
|
|
「獅子香炉」 ししこうろ
|
|
青銅 鋳造 玉眼嵌入
|
|
玉眼が嵌入され、上の獅子の頭が蓋としてはずせる構造。作者不明だが、
ユーモラスな造形がほほえましい。
|
|
作者不詳
|
|
|
「八手文電気スタンド」 やつでもんでんきすすたんど
|
|
江幡美忠 えばたよしただ
|
生没年不詳
|
|
「鬼花瓶」 おにかびん
|
|
青銅 鋳造
|
|
作者不詳
|
|
|
「牡丹置物」 ぼたんおきもの
|
|
青銅 鋳造
|
|
東京美術学校に金工三科がそろった間もない明治29年に文部省よりの管理換えで当館コレクションに加わった。
|
|
松原如方 まつばらじょほう
|
生没年不詳
|
|
「苞入魚置物」 つといりうおおきもの
|
|
青銅 鋳造
|
|
大島如雲の弟子、巴里美術学校卒。苞とはわらを束ねてものを包んだもの。ご馳走の伊勢海老を金属で表現。
|
|
白崎白善 しらさきはくぜん
|
1858-1925
|
|
「狆置物」 ちんおきもの
|
|
青銅 鋳造 真鍮・赤銅象嵌
|
|
鋳金の町高岡の白崎善平の流れを汲み、岡崎雪声、大島如雲、香取秀真ら率いる東京鋳金会で活躍。
狆はこの時代における愛玩用の人気モチーフのひとつ。
|
|
野上龍起 のがみりゅうき
|
1865-1932
|
|
「亀置物」
|
|
昭和7年(1932) 青銅 鋳造
|
|
三匹を別に鋳造し、蝋型鋳造の鋳肌と研磨仕上げと鏨彫りを使い分け、組み合わせている。
作者は大島如雲に師事し、東京美術学校依嘱制作の皇居前の楠公像や上野公園の西郷像の鋳浚仕上げを担当した。
|
|
「亀置物」(2点)
|
|
青銅 鋳造
|
|
野上は1900年のパリ万博にも、得意の写実と技巧を凝らした亀数点を出品。
|
|
金龍斎義道 きんりゅうさいぎどう
|
生没年不詳
|
|
「親子亀置物」
|
|
青銅 鋳造
|
|
香取秀真 かとりほつま
|
1874-1954
|
|
「瑞鳥銅印」 ずいちょうどういん
|
|
青銅 鋳造
|
|
香取は最後の帝室技芸員の一人。
本作は明治37年(1904)セントルイス万博に出品された東京美術学校出品の飾棚の四段目に配置された。
|
|
山田有方 やまだゆうほう
|
1871-1922
|
|
「銀製岩ニ鶺鴒置物」 ぎんせいいわにせきれいおきもの
|
|
明治30年(1897)鳥:銀・赤銅・四分一 脚:四分一
|
|
山田の卒業制作も明治37年セントルイス万国博覧会出品の東京美術学校出品飾棚の置物として選ばれた。
|
|
坂口晃南 さかぐちこうなん
|
1875-?
|
|
「龍筆架」 りゅうひっか
|
|
白銅 鋳造
|
|
明治31年美術学校卒業後、日本美術院に入り、
38年より東京美術学校助教授、昭和6年教授。本作は後の鎌倉市長正木千冬より寄贈。
|
|
佐藤省吾 さとうしょうご
|
1885-1983
|
|
「矮鶏」 ちゃぼ
|
|
明治43年(1910)銀 鋳造 赤銅象嵌
|
|
東京美術学校の彫金と鍛金が合併した金工科の卒業制作。
|
|
北原千鹿 きたはらせんろく
|
1887-1951
|
|
「多宝塔出現」 たほうとうしゅつげん
|
|
明治44年(1911) 四分一地 打出 毛彫 金色絵
|
|
昭和の工芸の改革を目指す「工人社」主宰として活躍することになる北原の卒業制作。
|
|
長沼守敬 ながぬまもりよし
|
1857-1942
|
|
「老夫」
|
|
明治31年(1898頃) ブロンズ
|
|
ヴェネチア王立学校で学んだ作家が1900年パリ万国博覧会に出品、
「鋳銅置物」として金牌を受賞した代表作。
|
|
|
|
3
|
|
山岸俊斎 やまぎししゅんさい
|
生没年不詳
|
|
「獅子置物」 ししおきもの
|
|
真鍮 鋳造
|
|
大島如雲、香取秀真、野上龍起、津田信夫などとともに東京彫工会で活躍した鋳金家の一人。
|
|
四谷正美 よつやまさみ
|
1876-1941
|
|
「真鍮製虎ノ丸彫」
|
|
明治32年(1899)真鍮 鋳造 岩は四分一 鋳造
|
|
明治32年彫金科卒業制作。
|
|
正清華峰 まさきよかほう
|
1874-1956
|
|
「荷曳牛車」 にひきぎゅうしゃ
|
|
青銅 鋳造
|
|
明治33年鋳金科卒業、津田信夫と同級生。卒業制作も当館所蔵。
|
|
藤川勇造 ふじかわゆうぞう
|
1883-1935
|
|
「兎」
|
|
明治43年(1910) ブロンズ
|
|
東京美術学校卒業後、フランスに留学中の作品。その後、晩年のロダンの助手を務めることになる。
|
|
オーギュスト・ロダン
|
1840-1917
|
|
「ユーゴー」
|
|
1883 ブロンズ
|
|
ロダンが多大な影響を受けたユーゴと初めて会った年に制作。
しかし、ユーゴはポーズをとることを拒んだ。平櫛田中コレクションのうち。
|
|
戸張孤雁 とばりこがん
|
1882-1927
|
|
「男の胴」
|
|
明治42年(1909頃) ブロンズ
|
|
作者はニューヨークで絵画を学んだが、
荻原碌山の刺激で彫刻に転じる。弟子の山本豊市(本学彫刻科教授)寄贈。
|
|
荻原守衛 おぎわらもりえ
号 碌山 ろくざん
|
1879-1910
|
|
「トルソー」
|
|
明治40年(1907) ブロンズ
|
|
画家をめざしてアメリカ、フランスに留学し、
ロダンの「考える人」に衝撃を受けて彫刻家になる。
本作は碌山記念館の石膏原型より鋳造。
|
|
「坑夫」
|
|
明治40年(1907) ブロンズ
|
|
第7回太平洋画会展(1909年)出品。
長野・碌山記念館の石膏原型より鋳造。
|
|